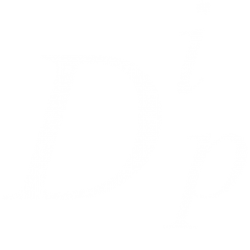本日(8/27)、特許事件(進歩性)の最高裁判決がなされました。争点は「発明が予測できない顕著な効果を有するか否か」です。
本件最高裁判決の判旨は以下の通りです。
原審は,結局のところ,本件各発明の効果,取り分けその程度が,予測できない顕著なものであるかについて,優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か,当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく,本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として,本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに,本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく,このような原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
最小三判令和元年8月27日(平成30(行ヒ)69)
正直なところ、思っていたよりも小振りな最高裁判決だったのですが、事件そのものは複雑でしたし、重要な問題を含んでいるように思います。
そもそも、本件最高裁判決の事件は、いわゆるキャッチボールという特許庁と裁判所の間で事件が反復してしまう現象が発生した事件であり、今回破棄差戻された原審判決もすでに第三次事件となっていました。
- 第一次事件:知財高裁平成24年7月11日決定 (平成24(行ケ)10145)
- 第二次事件:知財高裁平成26年7月30日判決 (平成25(行ケ)10058)
- 第三次事件:知財高裁平成29年11月21日判決 (平成29(行ケ)10003)
しかも、今回破棄差戻された第三次事件の原審判決では、以下のように付言までされていたのです。
特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは,審判官は特許法181条2項の規定に従い当該審判事件について更に審理,審決をするが,再度の審理,審決には,行政事件訴訟法33条1項の規定により,取消判決の拘束力が及ぶ。そして,この拘束力は,判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから,審判官は取消判決の認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって,再度の審判手続において,審判官は,取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと,あるいは上記主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではない。また,特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとの理由により,容易に発明することができたとはいえないとする審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には,再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果,審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないと認定判断することは許されない(最高裁昭和63年(行ツ)第10号平成4年4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号245頁参照)。
知財高判平成29年11月21日(平成29(行ケ)10003)
(中略)
発明の容易想到性については,主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか,当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり,当事者は,第2次審判及びその審決取消訴訟において,特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も,これを否定する事実の主張立証も,行うことができたものである。これを主張立証することなく前訴判決を確定させた後,再び開始された本件審判手続に至って,当事者に,前訴と同一の引用例である引用例1及び引用例2から,前訴と同一で訂正されていない本件発明1を,当業者が容易に発明することができなかったとの主張立証を許すことは,特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず,訴訟経済に反するもので,行政事件訴訟法33条1項の規定の趣旨に照らし,問題があったといわざるを得ない。
本件最高裁判決は、上記第三次判決でも引用された最高裁昭和63年(行ツ)第10号平成4年4月28日第三小法廷判決との関係において、どのように整理されるべきなのでしょうか?この点、調査官解説を待つしかないのかもしれません。
特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたと認定判断することは許されないのであり、したがって、再度の審決取消訴訟において、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りである(同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができた)として、これを裏付けるための新たな立証をし、更には裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違法とすることが許されない
最小三判平成4年4月28日(昭和63(行ツ)10)
二次的考慮説からの評釈(追記1月8日)
本日、田村善之先生の評釈がアップロードされましたので、メモ程度に少し書き留めておきます。
本件最高裁判決が独自要件説との親和性が高いということは、判決が出たときにすぐに気がついたことです。一方、本件最高裁判決が二次的考慮説を否定してしまったのかというと、必ずしもそうでもないのかなと思っていました。当初のコメントで「思っていたよりも小振り」と所感を述べた理由は、この点についてのものでした。
今回、二次的考慮説の論者として知られている田村先生の評釈が公開されたことによって、二次的考慮説の視座からの本件最高裁判決の理解の参考になります。なお、進歩性判断における二次的考慮説と独立要件説の違いは、田村先生の評釈においても説明されているので、これを参照するのがよいでしょう。
二次的考慮説は、発明に顕著な効果があるにも関わらず、これまで発明されていなかったということは、発明をなすことが困難であることを推認させるから、あるいは、効果を予測し得ない場合には発明をしてもそれが成功する合理的な期待がないからであるから、これを考慮することが許されるのだと理由づける。これに対して、独立要件説は、当業者が引例から発明の構成を容易に想到しうるとしても、当該構成に顕著な効果がある場合には特許権を与えるべきであると考える見解である。
Westlawjapan 判例コラム第189号
気を付けるべき点は、二次的考慮説の立場であったとしても「予測できない顕著な効果」を考慮すること自体は独立要件説と同じなのです。そして、田村先生の評釈の結論は以下のとおりです。
以上、要するに、本判決は、第一に、医薬用途発明については構成が容易想到であっても、予測しがたい顕著な効果がある場合には、進歩性が認められる場合があること、第二に、予測しがたい顕著な効果の有無を判断する際には、発明の奏する効果と対比すべきは、究極的には、発明の構成から当業者が予測しうる効果であること、の2点を明らかにしたものといえるが、とりわけ第二の点に関して、具体的な事例においてどのようにこの究極の対比対象を推認していくのかということについて、本件と同様の事案が出てきた場合を超えて幅広い射程を有するものということはできない、その意味で事例判決である。また、医薬用途発明を超えて一般的に、進歩性判断に関して、独立要件説をとるのか、二次的考慮説をとるのかということに関しては態度を明らかにしていない。既述したように、理屈をこねるのであれば、二次的考慮説には馴染みにくく、独立要件説に親和的ともいえなくもないが、明言していない以上、(その変更に大法廷を要するという意味での)判例の射程がそこに及んでいるとはいえないと解すべきである。
Westlawjapan 判例コラム第189号